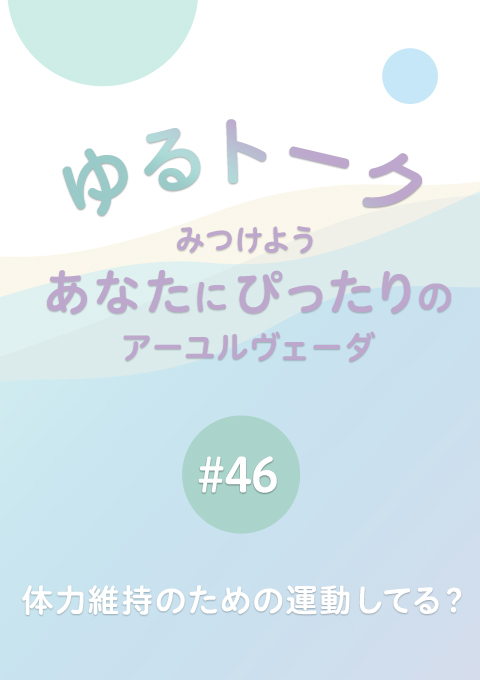ゆるトーク 〜みつけよう、あなたにぴったりのアーユルヴェーダ〜 #46 体力維持のための運動してる?
運動量 ● ● ● ● ●
ビデオクラスのご視聴には
プランの購入が必要です
新規メンバー登録から3日間は
無料で視聴できます
第46回は、体力維持のための運動してる? についてゆるトーク。 ヨガインストラクターも体力が必要なお仕事です。ふだんどのように体を鍛えているのでしょうか。体力を上げたり、柔軟性を高めるためには、実は少し負荷をかけることが必要だそうです。そのちょっとした負荷ってどのくらいなのでしょう? 週にどのくらい体を積極的に動かしているのでしょう? ヨガインストラクターのリカさんにお話しを聞いてみました。
自然体でいられる心と体の関係を追求しながら、何事も一歩踏み出す勇気をもち経験することをモットーに日々学びを深めている。
ヨギー・インスティテュート500時間認定
作業療法士国家資格
アーユルヴェーダ学会アーユルヴェーダ・セルフケア・アドヴァイザー
仏教教師資格課程修了
全米ヨガアライアンスコース500時間(RYT500)講師
メディテーション・ベーシックコース(MBC)講師
セラピューティックトレーニングコース講師
シニアヨガ・トレーニングコース講師
ヨーガニードラ・トレーニングコース講師
見つけよう!あなたにぴったりのアーユルヴェーダ。
こんにちは。
ヨガインストラクターのアヤです。
このプログラムでは、
アーユルヴェーダの知恵に救われ続けている、ヨガインストラクターのアヤが、
毎回ゲストをお招きし、健康や美容に関する、
日常に生きる、ちょっと役立つ知恵をお届けします。
進行のサポーターをしているしちさんです。
しちです。よろしくお願いします。
yoggyairのライブストリームでは、アーユルヴェーディックヨガのクラスを
毎週日曜日の朝10:30に私、アヤが行っています。
そして、隔週金曜日の夜20:30にヒロ先生が担当しています。
季節に合わせた体のケアの知識とともに、ヨガで体を動かしていくクラスです。
また、アーユルヴェーダ料理研究家の水野香織さんによる、
アーユルヴェーダキッチンを月3回月曜日の夜19:30に開催しています。
アーユルヴェーダの食べ物やハーブのお話、そして実際のレシピについても、お話しを聞くことができるクラスです。
ぜひ、クラスでお会いしましょう。
-

アヤ
今回は『運動』についてゆるトークします。
ゲストはリカ先生です。
どうぞよろしくお願いいたします。 -

リカ
こんにちは。
よろしくお願いします。 -

アヤ
お願いします。
アーユルヴェーダでの運動とは、 発汗療法の一つともされています。
そしてその目的は、体を強くすることを目的として、 体力を増大させる、好ましい身体的行動のこと、というふうに言われています。
リカ先生は、体力を維持・向上するために、 何か意識的に取り組まれたりされてますか? -

リカ
体力の維持・向上を考えたら、 年代的には少しずつ、少しずつ筋肉量が減っていく時ですから、 積極的に動いて負荷をかけていくことが必要だと思っています。
私は週に2回ほど、割と動く系のハードなヨガの練習を、外に受けに行っています。
その他は、自分の担当するクラスの前後に軽く動くくらいになります。
週に1回は、あえて何も練習しない日を作っています。
ただそうするとですね、一番だるいのが、練習しなかった日の次の日です。
週7日間ある中で、週2日間ハードな練習します。 残りの4日間はちょっと自分のクラスに支障がないくらいの軽めの練習。 1日だけは何もしないっていう、そんなリズムがあるんですけど、 何もしない日の次の日が、一番体が重くてだるいんですよ、不思議ですよね。 -

アヤ
そういう時は何をしますか? -

リカ
その日は、ちょうど自分の担当するクラスが3本あります。
午後からスタートなので、午前中軽く練習します。
そうすると動きやすさが戻ってきます^^
体力を維持しようって思うと、やっぱりちょっと負荷をかけないと…、
軽く動かす、軽く練習する、緩やかなものって思うと、 体の調整ぐらいにしかならないと思うんですよね。
ちょっと負荷をかけていかないと、やっぱり体力を向上っていうことを考えたら、 その向上は望めないので。
体力を上げていくってこともそうですし、 柔軟性を高めていきたいっていう思いが、 やはりヨガの練習をしているとそんな思いも大きくなってきますので、 ゆるいところでやっていると、やっぱりそこまででしかないので、 「あー、痛てててー」の場所を、ちょっと…変態だと思うんですけど、 強すぎても痛めますし、弱すぎても負荷がない、何も変わるってこと、 向上がないので、ちょっとずつ負荷をかけていくことを、いつもちょこっとプラスアルファの負荷、 そんな練習を大事にしています。 -

アヤ
なるほど。
もともと体力があるので、 ちょっとここを質問していいのか分からないですけど、 ちょこっと負荷ってどのくらいの負荷かけてますか? -

リカ
そうですね。
例えば、前屈のポーズだとしたらば、 ヨガでいうところの、よくある片膝を曲げて片足だけ伸ばして前屈するという、 ポーズ名だと…ジャーヌシールシャーサナという、 そんな前屈のポーズがありますけれども。
ただ片足伸ばしました、片膝曲げました、 両手を前に伸ばしていって前屈します。
それでも、もも裏側の伸びは十分感じられますけど、 それだと負荷少ないですよね。
なので、例えばそこから足先に手を添えて、つま先を手前に引っ張るとか。
あるいは足裏の向こうで、一般的によくやると思うんですけど、 片手でもう一方の手首を掴む。 肘を張る。 そして、肘を引く。
胸を前にさらに持っていくと、グッと負荷が高まりますので、 そういったポーズに入ってから、いかに負荷をかけていくか、 負荷が高いと、そんなに長い間キープする必要ないと思っているんです。
負荷が低いと、ある程度キープした方がいいと思うんですけど、 負荷が高いほど、キープ時間は少なくて効果的。
そんなふうに思ってますので、 ちょっと痛っ、のところから、もうちょこっとプラスアルファ強めに、 全てのポーズを心がけたりしています。 -

アヤ
なるほどですね。
ちょっとずつスパイスを足していくような感じですね。 -

リカ
いいこと言いますね~
さすが! -

アヤ
とんでもございません(笑) -

リカ
特に冬って、今この時期ちょうど2月の始めになりますけれども、 季節的なことを考えると、夏至の時が一番体力が弱くて、 の時が一番体力が高いという風にアーユルヴェーダで言うと思います。
なので、この冬場は特に動いて良い時期ですし、 どんどん楽しんで練習していけたら良いなと思っています♪
負荷をかける=きつい=しんどい。
大変だけど頑張らなきゃ!ではなくて、 楽しいって感じることを練習していきたいなと思っています! -

アヤ
そうですね。
アーユルヴェーダでも、運動をしていくときの心がけ、目安というのがあって、 その中の一つに、楽しんでやることというのが挙げられているんですよね。
なおかつ、脇とか額に汗をかく程度というのが目安になっていたりするから、 今日のリカ先生のお話を聞いたりとかすると、 自分にとってのどういうふうな負荷がけをしていくのか、 高めていったらいいのか、 そして週に2回以上ですかね、 やっぱりちょっとだけ自分で息が上がるような運動を心がけてみるっていうだけで 体力が上がるなら、ちょっとした心がけで取り組めそうな感じがしました。 -

リカ
はい!
楽しいって感じることが一番大事かなと思います。
私、最近特に練習の中で「逆転」が割と、 ここ最近は好きなんですけれども。
怖い怖いって思っていると、いつまで経っても上達できないんですよね。
いつまで経っても壁から離れられないんですよ。 私もそうなんですけど(笑) なかなか上達が進まないんです。
あんまりヨガの経験もそれほどなくて、 そんなに柔軟性も…私から見てですけど、それほど柔軟性も高いわけではない、 体の使い方がすごい上手で繊細というわけでもない方がですね、 すごい楽しく練習されているんです。
そういう方のほうが、意外と逆転に関して言うとチャレンジできるんですよね。
楽しんでるから、壁がなくても、楽しく遊ぶように練習している、 すごい上達が早いんですよね、やっぱり。
あれこれ考えすぎず、これはこうじゃなきゃ、 ここをああしてこうして、こうやらなきゃとか、あんまり難しく考えることなく、 自分にこうじゃなきゃっていう思いを課すことなく、 楽しんでいる方ほど、上達も早いなと、そんな風に感じてますので、 私も遊ぶように、逆転の練習をこの先もちょっと…、 特にですね、ここ冬から春にかけて、特化して、 遊びながら練習していきたいと思っているところです。 -

アヤ
すごいですね♪
あの…ちょっと事前の収録の前にですね、 「逆転のポーズどんなことしてますか?」って言ったら、 いろんなバリエーションの逆転のポーズのお話をしてくださいましたので、 そこらへんはまた直接お会いして、伝授を仰いでいただけるといいかなと思います。 -

リカ
はい。
ぜひぜひお声掛けをお待ちしています! -

アヤ
はい^^
今日はありがとうございました。
今日の知恵はいかがでしたか?
運動について、リカ先生にお話を伺いしました。
ポイントとしては、ちょっとずつ自分の負荷量を上げていくこと、 そしてリラックスすることだけではなくて、 ちょっとだけ大変だなって思うような負荷がけをしていくことっていうのを、 週の中でも2回ほどやっていかれると、 今の体力というものが維持できるんじゃないかという一つの提案でした。
日常に生きるちょっと役立つ知恵、次回もお楽しみに♪