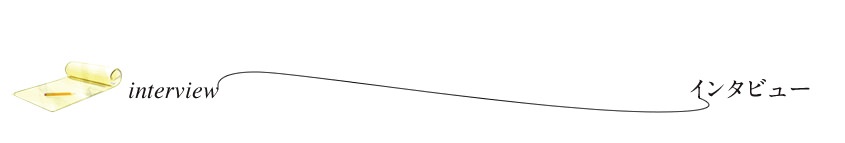
誰も悲しんでないか、みんながハッピーか。目の前のモノがどこからきたかを想像する。

葭内 「エシカル」とは英語で“倫理的な”と言う意味です。つまり環境や社会貢献を意識したファッションのことです。「フェアトレード」、「リサイクル」、「オーガニック」などをひっくるめて、オシャレを楽しみながら、社会にも貢献しようという考え方です。
――知らない人には、ちょっと難しいことのように聞こえますね。
葭内 そんなことはありません。最近はデザインなども素敵で、素直にほしい、と思えるエシカル商品もぐっと増えているんですよ。自分の目の前の物が、どこで誰がどうやって作っているかを想像することがエシカルなんです。社会や環境にどう影響するか、誰も悲しんでないか、みんながハッピーか、そういうことを気にすることが大切なのです。たとえば、生産者の人権を守り、適正な価格で取り引きされるフェアトレードの洋服を着れば、途上国の人たちの暮らしをよくすることにつながります。
――葭内さんは、国内で初めて高校の家庭科の授業でエシカル・ファッションを取り入れたとか?
葭内 はい。私が授業で初めてエシカルファッションを取り上げたのは、2011年です。まだエシカル元年と言われていて認知度もありませんでした。授業の内容はエシカル・ファッション自体を教えるのではなくて、消費の背景への眼差しを育てることが目的です。生徒にアンケートを取ると、洋服を買う時に誰が作ったかは考えないし、本当に安くてかわいくて、自分の好みであればそれでいいという、態度が大半です。自分が手にしたものが誰かのダメージになっていないか、ハッピーになっているかを考えるようにさせたい。授業では、とにかく生徒に体験をさせたい。「伝統技術」というのもエシカルの要素なんですけど、過去には四国の藍染め職人さんと連携して、インターネットを通して藍染作業を見せてもらいながらやりとりして、実際に藍染めを実習しました。そして体験をしてから初めてエシカル・ファッションは何かということを解説するのです。

日々、生徒に心が動かされる
葭内 教育していると、日々、心が動かされます。感動して泣いてしまうことも結構あるんですよ(笑)。ですから、一つには絞れないですね。驚くというよりは、若者ってやわらかいし、発想が豊かだし、いろんな意味で入りやすいなと感心します。生徒は「すごい!」って素直に感動しますね。大学生にも教えているんですけど、中学生の方がモノの受け取り方のやわらかさが違う。ただ中学生にくらべて高校生は何がいいかと言うと、実際の生活で行動に移せる。たとえば、エシカルの授業をした後に、勝手にチャリティイベントをやっている子もいました。自発的にNGOにボランティアに行く子とか。すぐに実際の行動につなげる力が高校生は強いなと思います。
――今ではエシカル・ファッションが家庭科の教科書でも取り上げられているとか。
葭内 私が編集委員を務めた東京書籍の家庭科教科書に「エシカル・ファッション」についてのコラムや記事を掲載しました。日本では初めてのことです。この教科書はシェア1位にもなりました。全国の高校生にエシカルマインドが広がればと期待しています。

社会に何ができるかを考える
葭内 父親には「社会に何ができるかを考えなさい」と言われていました。実際に父が自費で熱心に社会貢献活動をしているのを見て育ちました。両親は当時まだ始まったばかりの途上国の子どもの教育支援プログラムの里親にもなっていて、中学生の私も、支援しているインドの子どもなどと英語で手紙のやりとりをしたりもしていました。ですから、家の中に、社会貢献の考えがあったと思います。思想の方向性は多分親からもらったのだと思います。
――ずっと家庭科の先生になりたかったのですか?
葭内 いいえ、始めはご縁があって教えることになりました。でも教えているうちに、家庭科は、生活全体を、科学や政治、経済の視点から俯瞰して捉え直して日々の実践につなげる、ジェネラルなライフサイエンスだということがわかり、とても面白くて大切だと思いました。生きることの根幹に関わり、教え方のアプローチも様々な可能性があるとこころも魅力です。
――将来の夢はありますか?
葭内 今、エシカルに関心のある層は女性、そして意外と20代男性です。でも社会的な決定権が強い40代後半から50代男性は興味が希薄です。その辺りの層にエシカルを伝えたい。そこが社会をガラッと変えるところになると思います。夢というよりも目標ですね。

写真/ 文 美濃部 孝




