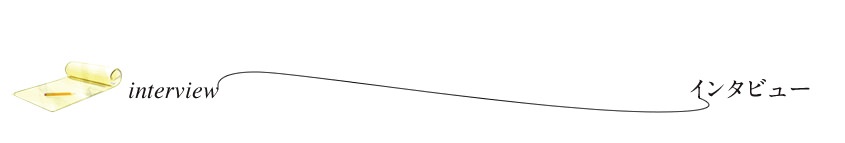
家族以外の大人も関わる、多様な「子育て」が文化になっていく社会を

小澤 はい。妊娠期から20代くらいまでのお子さんがいるご家族やお子さん本人からの、例えば発達の特性があって今の環境でうまくいかないという相談に対しての環境設定や、様々な虐待を受けながら、その環境で生き抜いてきたお子さんのケア、養育が困難なご家庭のケア、子どもに関わっている保育教育機関などに出向いての相談などを行ってきました。5月からは、「PiECES_」(ピーシーズ・DICから団体名を変更)という団体での活動を主にやっていきます。
――どんな活動内容なのですか。
小澤 ”何かあった時にその時点から関わってそれを支援する”、から、子どもの「育ち」に……大人の側からの言葉「育てる」ではなく、子ども自身にとっての成長を意味する言葉として「育ち」を使うことが多いのですが、その育ちに、”普段から社会とのつながりが当たり前にある状態”をあらかじめ作っておくことが必要ではないかと思っていて。対等な関係性の中で、受容される、とか新たな機会や経験を通して希望がみえるとか、もっと様々なつながりが何も起こっていないときからあるといいなと。機会や経験の格差がなくなっていくことで、予防につながったり、子どもたちと環境の間にうまれる困難が困難でなくなったり、乗り越えていけたりということが可能になると感じています。子どもの育ちの過程に、家族以外の人も関わる「拡大家族」というか、”家族だけで育てる”、から”社会で育てる”文化が醸成されていったらよいなと。そのためのしくみを作ろうとしています。
――具体的にどんな形を考えているのでしょう。
小澤 それぞれの家や企業に「文化資本」みたいなものがあると思うんです。現在は、それを開いていただきながら何かあってからでなく、普段から子どもの育ちに家族以外の大人が関わるということをやっています。
――文化資本ですか。
小澤 例えば「この家はみんなでごはんを食べる」とか「この家にはこのマンガが全巻揃っている」「この家では音楽ができる」というのも文化資本のひとつです。それにプラスして、子どもの育ちに必要なもの……無条件の存在受容みたいなものがあったり、社会のルールをちょっと教えてくれる人がいたり、社会の中での存在承認があったり、それぞれが持っている資質とか得意なものを、少しずつ外に開けるといいなと。
「あの家にはごはんを食べながら、受容してくれる人がいる」というような。家以外の大人からも受容されたり社会化を学んでいくことができる環境。他の人が育ちにたくさん関わる新しい拡大家族の形と、そこで子どもの育ちに必要なものがちゃんとある環境を通して、子どもも大人も、色々な家族との形や生きる形があってよいし、それでも大丈夫なんだ、と思っていけたら。
今は足立区と豊島区にそういうお宅があって、近所の方が食材を持って集まって料理してくれたり、子どもたちが自分で料理をするようになったりしています。

小さな選択の積み重ねが、その人の尊厳を作っていく
小澤 そうなんです。場所や人や、そこに信頼でき安心できるつながりがあることが大切だと。さらに、本人がそれを自分でポジティブに選択できるような環境設計ができるといいなと。学校に行けないから、家がこうだから仕方なく、そこしかないからあそこに行くということじゃなくて、自分が漫画を読みたいから、ごはんを食べたいから、あの人に会いたいから、ここに行きたいから行くんだ……そういう小さな選択の積み重ねが、その人の尊厳を作っていくのかなと思います。
活動をする中でより予防的な視点の必要性を考え、子どもが産まれる前、妊娠期から親御さんが自分だけで頑張らなくてよいようなつながりをつくれたらとも思っていて。お母さんをエンパワーし続けてきた方がいるんですが、彼女と一緒に妊娠期から既に子どもの育ちに他の人が色々な形で関わっている状況を作ろうとしています。
協力してくださる企業もあって、ありがたいです。雇用体系の変化や新たな雇用創出に力を入れようとしている企業もあり、私たちの活動と通じるところがあり、無償で場所を提供してくれたりしています。企業と一緒に活動するのは、本質を変えていくというところでも大切で。大事なんですよね。働き方が多様な形に変化し、雇用体系や保障のところも変わっていかないと、子どもの育ちに関わる大人の生活が固定化したままになり、子どもの育ちのところもなかなか変わっていかないと思います。

きっかけがあれば、人の可能性は広がって行く
小澤 小6で祖父が亡くなったことがきっかけです。初めて接する死でした。胃がんだったんですが、ずっと我慢していたようで、わかった時には手術もできない状態だった。その時に、医学でもっと予防的なことができないだろうか、と思いました。
精神科医に興味を持ったのは高2の時です。友人が摂食障害で亡くなって。摂食障害がベースにあっての自殺だったのか摂食障害自体でなくなったのかはわかりませんでしたが。その時感じたのは、人が亡くなるとその人の周囲は変化がおこる、けれども社会自体は一人の死でそんなに変わらないんだ、ということ。社会と人との関係や、そもそも生まれた途端に死に向かって生きていることや、いわゆる思春期に考えるようなことを考える中で、哲学書を読み漁った時期があり、そこから精神医学興味を持つようになりました。
祖父の死はどうにもならない死でしたが、この友人の死はどうにもならない死じゃないというか……そもそも例えばその人が自分で命を断ったとして、その死を止められたかもしれないなんておこがましいしエゴだと思いながらも、ただ死にたくなる前に、「死ぬ」ではない選択肢をその人自身が選択したり考える機会は、周りとのつながりで作れたりするのかもしれない、というのをその時考えていました。
小澤 大学に入って、学校に行っていない子どもの家庭教師をしたり、養護施設のボランティアをしたりして、そこから児童精神科に興味を持ちました。もうひとつは、両親が高校教師だったのですが、普段から生徒たちが家にたくさん来ていたんですよ。家族以外に遊んでくれるお兄ちゃん、お姉ちゃんがいる、みたいなことが日常でした。ただ、子ども心に複雑な事情があるんだろうなあ、というのもなんとなくは気づいてはいました。うちに家出してくるお姉ちゃんがいたりしたので。そんなお兄さんお姉さんが何かあったらふらっと家に来て、を繰り返しながら、気づいたらしばらく来なくて、次に来たときは結婚とか仕事の報告にきていたりというのを間近でみて育ちました。
――現在の活動に、ご両親からの影響も大きそうですね。
小澤 大きいと思います。両親自身が自分たちの信念はあるのだけれど、「こうあるべきだ」という固定観念をあまり持たずに生きていて。社会的にこういわれてるから、というところに囚われずに、当たり前や社会通念を疑うというか、問いなおす視点をもつ大切さを言われてきました。疑問をもったら考えてやってみたらいい、を実践してきた人たちで。今、そのことに感謝しています。
――小澤さんにとってのアート・オブ・リビング、魂が震えるような出来事を教えてください。
小澤 様々な子どもや家族に出会ってきて、それぞれの力や変化を目にするたびに、人の力に感動しています。例えば、シビアな環境の中、感情をものすごく抑圧して、感じる事自体をしないことで自分を守っていきてきた子がいて。その子は何かあるとそれが死にたい気持ちにつながりやすく、楽しいとか嬉しいとかそういった感情がわからないと言っていました。周りの人たちの関わりやケアの中で、感情を感じたり出したりしながら、人との関わりが増え、好きなものが増え、すこしずつ変わっていきました。
彼女は絵で表現することがすごく得意だったのですが、それを周りから言われて初めて気付き、日々の中で何かあると絵をお願いされるという役割ができ、その後、自分の描いた絵が人の力になるんだ、という経験を積んでいった時の彼女のさらなる変化をみながら、人は誰でも、その人なりの力というか素敵な資質を持っているんだとあらためて感じました。それを奪っているのは環境なんですよね。きっかけ様々だと思いますが、そのきっかけの格差はなくしていきたい。よいきっかけがあれば、人の可能性はどんどん広がっていくのだと思っています。
写真 野頭 尚子/文 門倉 紫麻




