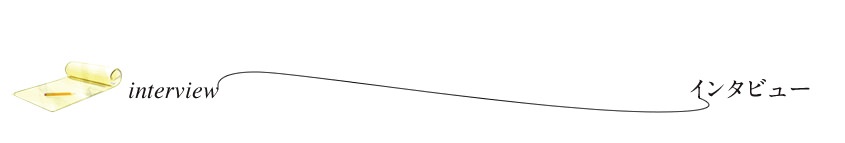
あいまいで頼りない感覚が外に出すことで確信に変わっていく

ここまで無防備に、自由になれる人がいるんだ、と思いました
野頭 はい。作家の吉本隆明さんの撮影で起こったことです。
――これがその時の写真ですね。とてもチャーミングで、素敵な写真ですね。
野頭 ありがとうございます。もう16年くらい前、28歳の時です。当時私が師事していた写真家の方のスケジュールが合わず、アシスタントの私が代わりに撮影することになりました。なので、初めて「仕事」で撮った写真です。この撮影の後、それまでやっていたファッション撮影の仕事はやめて、一刻も早くポートレートの勉強をしなくては!と思いました。
――それほど強く心が動くような経験だった。
野頭 衝撃的でした。前の日は寝られないし、当日もお寺ですごく時間をかけてロケハンをしたりと準備を整えて。でも、いざ撮影になったら、最初の何枚目かでもう「これ」という写真が撮れてしまったんですよ。すごく不思議な感覚で。ただシャッターを押しているだけというか……私が撮っているという感じじゃない。こうしてくださいとか吉本さんに指示を出したり、作為的なことを何もしなくても、撮れた。
――なぜそんな撮影になったのだと思いますか?。
野頭 なぜでしょうね……吉本さんの全部をさらけ出す感じがそうさせた、というか。見ず知らずの人に、ここまで無防備になれるのか、と思いました。あんなふうにガードをなくすことは私にはできない。吉本さんは、本当に自由になれる人なんだなあと思いましたね。
――それでポートレイト撮影というものに魅力を感じた。
野頭 そうですね。撮影した感覚があまりにも不思議で、これってどういうことなんだろう、もっと撮ってみたいと思った。その時は「吉本さんが」すごいんだ、とは気づいていなかったですね。

時間と引き換えにお金をもらう?
野頭 25歳くらいまで生命保険会社にいて、証券会社の担当をしていました。
――だいぶ写真とは違う世界にいらしたんですね。
野頭 そうですね。まだバブル期だったので、就職活動も気楽な感じでやっていたんですよ。バイトの合間にいろいろな所に面接に行って、たまたま受かった、というような感じで入社しました。同僚はみんないい人たちで、今でも仲がいいくらいなんですよ。楽しい会社でした。
――辞めようと思ったのはなぜですか?
野頭 ある時、その会社にいた場合の自分の未来が見えてしまったんです。30歳になったらあの役職に就いて、年収はいくらくらいになって……と。それが、なんだか時間と引き換えにお金をもらうことのように思えてしまって。だとしたら、その時間がもったいないなと思った。証券会社を担当していたので、まさにバブルがはじける瞬間を現場で直接見てしまった、というのもありましたね。
――経済のど真ん中にいたんですね。バブルがはじけるのを見て無常だな、と?
野頭 そうですね。証券会社でひどい辞めさせられ方をしている人を見て、「会社」というもの自体に疑問を持つようになって。私のいた会社はとてもいいところだったし、これ以上いい会社はないだろう、とは思っていた。ならば次は会社員ではない道を選んで手に職をつけたい、と。じゃあ自分には何ができるかなと考えて……大学時代に写真館でバイトしていたこともあり、写真の仕事を考えるようになりました。
「カメラひとつでどこかに行きたい」と思った
野頭 いえ、いきなり撮影スタジオにアシスタントで入りました。バイト先だった写真館にも誘っていただいたんですが、「カメラひとつでどこかに行きたい」という気持ちが強かったので、ひとつの場所にずっといるのは違う気がして。それでまずは、スタジオのアシスタントになって技術を身に付けよう、と。
――スタジオの仕事はハードだと聞きます。
野頭 最初に入ったスタジオは、日給5000円で朝から朝までって言う感じでしたね。友だちが自給を計算してくれて「198円だよ、いいの?」って(笑)。仕事内容は全然大変ではなくて、窓の開け閉めと簡単なライティングくらいで、アシスタントがやれることがほとんどなかった。これでは技術が身につかないと思っていました。
――そこから別のスタジオに移られたんですね。
野頭 はい。別のスタジオから撮影に来ていたアシスタントさんたちが、すごく仕事ができる人たちで。私もこういうふうになりたい、と思った。それでバイトをやらせてください、とお願いして、そのスタジオに移らせてもらいました。
――会社を辞めてからどんどん先に人生が進んで行きましたね。
野頭 今思うと、あの時が一番、人生がうまくいってたかもしれない(笑)。でもその頃ってちょうどhiromixさんとか女の子のカメラマンがたくさん出てきた時期で。スタジオの人には「まさか、カメラマンになれるなんて思ってないよね?」と言われたりしていましたし、私も「思ってないです!」と答えていました。私は特に美大を出ているわけでもないし、まあ、確かになれないよなって。スタジオ自体はとてもいいところで、仕事は楽しかったんです。ファッション関係の写真をたくさん撮っているスタジオでした。
――ファッションには興味があったのでしょうか。
野頭 いえ、まったく(笑)。でもファッションの仕事って、チームで作っていくものなんですよね。それがとても楽しくて。とにかくおもしろい人がいっぱいいた。撮影中にはじのほうでキャッチボールをしている人がいたり、寝転がっている人がいたり。そういう雰囲気が、とてもよかった。
――そこで出会ったファッション系の写真家の方に師事するわけですね。そして吉本隆明さんとの出会いへつながる……と。野頭さんのお話を聞いていると、会社員時代からずっと、自分のいる場所自体に大きな不満を持ったりはしていないですよね。常に「おもしろい」と思っている。ただ、ほかの道が見えたのでそちらへ行くことにしたのだ、という感じがします。
野頭 そうかもしれませんね。吉本さんとお会いして、ポートレイトを専門にしたいと思ってからも、結局3年くらいはその師匠のところでアシスタントを続けていました。業界のトップにいる人の仕事を長く間近で見られたことは、本当によかったと思っています。
大きな出来事は「なんてことはない」感じで起きている
野頭 最初の撮影から8年後、『ひきこもれ』という書籍の仕事でした。その時に、前回撮影した写真をお渡ししたんですよ。そうしたら漫画家をしていらっしゃる娘さん(ハルノ宵子)が「あら、お父さんよかったじゃない、お葬式の遺影ができて」って(笑)。そういう「普通のおうち」なのもいいなあ、と思いました。
――前回撮影した時のような感覚になりましたか?
野頭 なりませんでした。吉本さんはやっぱり素敵な方だなあとは思いましたが、あの感覚ではなかった。ああいうことって、なんてことはない感じで起こるから、その時はよくわからなくて。だけど、あとから「そんなに起こらないことなんだ」って気がつく。
――わかる気がします。
野頭 何かに出会って「なんかいいな」とか「すごいな」と思っても、それは自分だけの感覚だから、すごくあいまいで、頼りないものですよね。でも人に見せて「いいですね」と言ってもらえたりする中で、確信的なものに変わっていく。もちろん誰かに見せたらコテンパンに言われて、折られてしまう可能性もある。それでも、その感覚を大事にして、どんどん外に出している人を見るとすごいなと思うし、私もそうできたらいいなあと思っています。
メイン写真 平野 太呂/文中写真 野頭 尚子/文 門倉 紫麻




