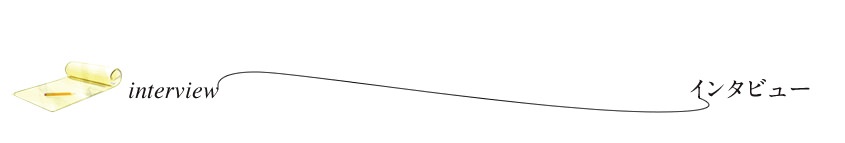
心で感じ、味わって出会った自分の生きる道

波の裏側にはありのままの美がある
杏橋 撮影するときファインダーをのぞかないので、最初にフィジーで撮影したときも、どんな風景が撮れているかすぐには分からなかったんです。日本にフィルムを持ち帰り、現像した写真を見たとき、「うわぁ!何だこれ!」って(笑)。色も形もこれまで目にしたことがない風景で、見た瞬間「これが撮りたかったんだ」と、心が強く揺さぶられたのを覚えています。
杏橋 波が作り出す風景は、一期一会。そこには、偽物でも本物でもない、ありのままの美しさがあります。波が崩れる様は“死”かもしれないけれど、その波の下では小さな魚たちが生きている。その死生観を美の中に感じ、強く惹かれました。

自分の心の状態を繊細に観察すること
杏橋 自由に海を感じたいので、酸素ボンベなど、人間本位の道具は極力身に着けずに、生身で海に入ります。そして、たった一人で、透明な紺碧の海で立ち泳ぎをし、あの波の中に入るにはどうしたらいいのか思いを巡らせながら、波を待つんです。そして、これだ!という波が来たら大胆に鋭く潜り込み、波をかわしつつ崩れ去る波を瞬時に観てシャッターを押す。そして水の流れにのりながら呼吸を求め光へ向かう。それは、一瞬でも迷いがあれば死につながる危険な行為ですが、自分にとってはかけがえのない瞬間なんです。
――恐怖は感じませんか?
杏橋 恐怖……。なんとなく克服したかな(笑)。じつは、波の裏側を撮り始めたころ、おぼれかけたことがあります。でもそれは自分の力があまりにも足りなかったから。そのとき、その足りなさを海に押し付けて、海に自分を殺させるのは申し訳ないと思ったんです。海は雄大な存在なので、人間が海のルールに寄り添えば受け入れてくれる。なので、撮影するときも、こう撮ってやろうという思惑や作為は捨て、撮らせてもらうという低いスタンスで、自分を海に合わせていくようにしています。
――どのように、波の裏側に行く術を身につけたのですか?
杏橋 誰も波の裏側に行った人はいないので、とにかく自分で体験しよう、と。身をもって、波の硬さ、弱さ、美しさ、冷たさという体感を深めていきました。ライフガードの資格も持っているので、最低限の知識や泳力はありましたが、何度も波と向き合うなかで、心の状態を繊細に観察することの大切さが分かりました。なので、緊張の糸が切れたときは、すぐに岸へ帰るんです。そして、もうひとつ大切なのは、海に対して礼を尽くすこと。純粋な行為として、忍や昔のネイティブな人々のように、祈りの言葉に心をのせるようになりましたね。

迷ったら、行動し、感じる
杏橋 何かに迷ったら、頭で考えすぎないで、行動し、感じること。一歩がなかなか踏み出せないこともあるけど、それは限界を自分で決めてしまっているから。僕の場合、これまでの生き方や考え方を捨てたり変えたりして、一歩踏み出したことで、ライフワークとも言える表現方法に出会ったし、海との新たな関わりも見つかりました。
――都心にアトリエを構えていらっしゃいますが、海が恋しくなりませんか?
杏橋 今後はもっと海と過ごす時間を長くしたいですね。でも、もし無人島に住んでいたら、こんな写真は撮っていなかったかも。地に足のつく世界と行き来することで海がなおさら愛おしくなるし、大切な場所だって感じると思うんです。
――今後も波の裏側を撮り続けますか?
杏橋 以前のように「撮らなくては」とは思わなくなりました。海のことをだいぶ理解できたし、今はいつ死んでもいいって思えるくらい自己満足しています(笑)。自分が満たされていないと人間って輝かないんじゃないかな。だから、自分に正直になり、入れ物の自分と魂の自分をつなげて、本当に自分らしく生きているか、を追求することが大事なんだと思います。
写真 野頭 尚子 / 文 小口 梨乃




