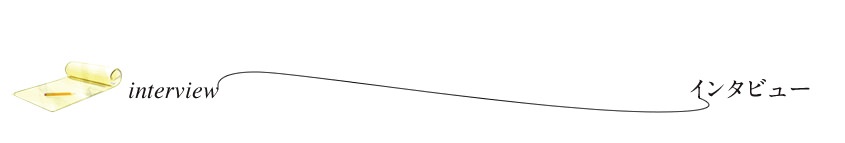
イベントリポート 後編 4月25日(土)映画「バベルの学校」ゲストトーク
Art of living magazine event vol.1

自分がマイノリティだと感じることはありますか?
七戸:けっこういろいろお話うかがったんですけれども、残りの時間を、小澤さんに質問してみたいことを、みなさんからいただきたいと思います。
Q. 精神科の領域ってほかに比べたら花形ではないので、どっちかっていうと下げて見られるというのがあると思うんですけど、今回の映画をみて、マイノリティの人が集まった映画だったので、小澤先生もそういうマイノリティのようなことを感じることはあるのかな?と思ったんですが。そういう経験があれば、お話していただけませんか?
A(小澤さん). そういった意味で、たしかに私自身、児童精神ってさらにニッチな分野なのでしょうけど、児童精神科が少ないとか、そういったところでは、マイノリティに感じたことはある…のかな。自分自身個人がマイノリティなんだろうなと感じたことはあっても、自分の医療の分野でそういえばマイノリティかどうかは感じたことはないかもしれません。
会場に、知り合いの児童精神科医の人が来ているから聞いてみたくなりました。
七戸:聞いてみましょう!
小澤さん:K先生、ありますか?
K先生:そんななんか、まわりとかの関係で悩むみたいなのはそんなにはありません。割と小澤さんの感覚と近いです。
七戸:そういうのはあるかもしれないですよね、分野とかで。会社で考えても。会社によって営業が花形、とか、事務はどうで、みたいに思いがちですよね。だけど思ってるのは本人とか場の雰囲気でもあるかもしれないけど。小澤さんや、先生はあまり思われない、ということですね。
小澤さん:なるほど、と思いました。
みんなをうまく導くには、どんな接し方がいいのでしょう?
A. 私自身もそこはとても興味があるところで。映画をみて感じたのは、あの先生自身が1人1人に向き合うなかで、その人の孤独とか葛藤とか自分の背景をちゃんと表現して共有するプロセスをとても大切にしていること、個々それぞれの表現を引き出している、というところです。表現は言語以外にもたくさんあるのですが、お互いが理解していく上で、言語として表現することで共有できていって。共有ができないと、もしかしたら限りなく一人なんじゃないかと思うんですよね。そういう意味で、表現し、共有する環境をつくりながら、さらに、子どもたち自身が表現できる力に気づくきっかけをつくっていることもとても素敵だなと思いました。エデュケーターって引き出す意味があると思うんですが、まさにエデュケーターだなと。私自身ももっと学べたらなと思っています。
七戸:引き出すっていう力も特殊というか、技術ですよね。
小澤さん:そうですね。本当に。ほんとあの先生の力すごいな、と思いますよね。子どもたち自身はその子どもなりの表現方法をもっていたり、気づいていったり、力もあるのはもちろんですが、それをさらに引き出したり、いろんな違いのなかで、これって自分の資質なんだと気づくのって、まわりとの関係性だと思うんですよね。大人には本来それを引き出力があるのかなとも思っています。それに意味付けやこちらの価値観をいれずにただ認めていくことや、本質的な問いをなげて、さらに子どもの問を引き出したりとか。たぶんそういったちょっとしたひとことが子どもの気づきとか、引き出すことにつながるという意味では、どんな大人も、その力をもっているのかなと思っています。
出来上がった大人にも、素晴らしさをシェアできる?
A. もしかしたら自分が経験したことだったらできるけれど、そうじゃないことは難しいって方もいるのかなと思います、そうでない方ももちろんいますが。まずは、大人同士でもそうだと思うんですけど、その人自身にももともと持っている資質や、素敵なところだったりとか、その人の力があると思うんですよね、そこを周りの大人が伝えていくとか認め合っていく、大人も誰かから認められた経験して初めて、子どもに対してできるのかなと思います。子どもに対してできない背景には、その人が経験してきたいろいろな背景があると思うので、その人の資質を周りがちゃんと気づいていく、というのがすごい大事かなと思います。
アートを通して子どもの可能性を引き出すとは?
A. 私はお花をやっていたりとか、バレエをやっている友人と一緒に表現を通して子どもたちの学びを親も一緒にみる、みたいな場所を前つくっていたんです。子どもたちは、言葉にはならないけどいろんな表現を知っていたりするんですよね。たとえば、その表現には正解はまったくなくて、子どもたちが正解がないなかで表現していくプロセスを大人たちがその事実だけを言語化したり、表現したときの感情を言語化したりして、子どもたちとのやりとりをしていくということをやっていました。そこも大人の価値観を入れずに、あ、いまこういうことをしたんだね、というふうに。大人の価値観、例えばこれをしたからえらいね、とか、いい子だね、という価値観をいっさい入れずに、ただ子どもの行動をそのまま言葉にしていく、大人がそこについていながら、みていながら、子どもが自由に自分の表現していくみたいな環境をたくさんつくっていた時期がありました。
正解がない中で子どもって自分なりの表現をしていきます。最初は、周りからの影響で、周りが求められるものを、とか、周りと一緒にというような価値観がある程度できていて、こう作らなきゃと思っていた子どもも、一人の子が崩しだすと、あ、なんかいろんな表現していいんだ、と、新しい表現の仕方を学んでいったりとか、自分の感情を出していったりとか、いろんなプロセスがあって、どんどん本来の表現したい欲求があらわれてきて。子どもの力を感じていました。
七戸:いまのお話のなかで、そのまんまを受け取るというところが、新鮮ですね。褒めたほうがいいんじゃないか、ってつい思っちゃうんですよね。でも褒めること自体が、評価になってしまう、と前おっしゃてたかと思うんですが。それがすごく新鮮だったんですよね。そのままを受け取るってなかなかふだんしていないかもしれないと思いまして。
小澤さん:見てくれている人がいるんだ、とかそういうふうなことが大事かなと思っていて。ただ行動をそのまま言葉にしていったり、それ自体も子どもが自分をみてくれていると思うことにもなりますし。
七戸:だいたい何歳ぐらいのお子さんたちなんですか? アートの場を作ったりしたのは。
小澤さん:もともとアートとかasobi基地とかは、幼児さんが多くて、乳児さんからお母さんが来たいと言ってくださって、乳児さんからだいたい小学校低学年くらいまでの方。
七戸:そうなんですね。
最後に、小澤さんのほうでこれからの活動で目指していることなど、いまいちどお話いただいていいですか?
小澤さん:子どもの育ち多様な大人で支える生態系をつくっていくことですね。
子どもの育ち、子育てとなったときに、それは親がするもの、とか勉強は学校でするものとか、子どもの成長にまつわることって、まだまだ他人事になったりしやすいものだと思うんです。同時に、教育や子どもって考えたとき、自分事ではないけれど、決して無関心ではないのかなと。そこをもっともっとたくさんの大人とか学生さんとかと、色々な関係性をつくっていきたいなと。その関係性が、子どもにとっての何かのきっかけになるとか、希望になるとか、何かおこってからつながるのではなく、子どもの育ちには多様な大人が関わっていること、それ自体が当たり前になっていくような文化を作っていきたいな、と思っています。そのためには私たちだけではできなくて、いろんな人の力が必要なので、そういったところをみなさんとと作っていけたらいいなと思っています。
――この日は、約40名の方にご参加いただきました。小澤さんの柔らかい雰囲気と、「映画の先生みたいに、日本人の方が実際に子どもの教育に取り組んでいて、嬉しかった。大人としてお客さんに対等に話してくださるのが誠実に感じました。」と、感想をお寄せいただきました。
アート・オブ・リビングマガジンでは、随時こういったイベントをおこなっていく予定です。Facebookやオンラインで告知してまいります。
イベントリポート前編は、こちら。
写真 野頭 尚子/文 Art of living magazine 編集部




